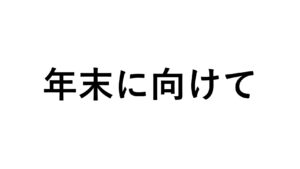バランス訓練
こんにちは!熊本市南区のリハビリ強化型デイサービスセンターあ・ふる~るです。
今回はバランストレーニングについてお話していきたいと思います。
まずバランスの取り方として大きく2種類に分けられます。
➀『重心をコントロールする方法』
②『支持基底面を移動させる方法』です。
➀については、
基本的には重心は支持基底面内に留まっていますが、何かしらの影響を受けて重心が支持基底面から逸脱しようとします。すると反射的に身体を動かして重心を支持基底面内の安定する位置に戻そうとします。このバランス反応として【足ストラテジー】、【股ストラテジー】というものがあります。
下図のように重心の逸脱や動揺が小さい場合は足ストラテジー、逸脱や動揺が大きい場合は股ストラテジーが働きます。
![]()
![]()
 ↔
↔
 ↔
↔
②については、重心が支持基底面から逸脱してしまい、身体の動きで重心を戻すことが難しい場合は支持基底面を移動させる手段を取ります。これをステップ反応といいます。
下図のように足を重心が逸脱した方向に出して、重心が支持基底面内に収まるようにします。
 ⇒
⇒
主にバランス反応としてはこの2種類になります。
※バランスを崩したときに手すりなどの支持物につかまる行為は今回は省きます。
まずはストラテジーを強化していきます。足や股関節の可動域や筋力等の評価をしたうえで、実際に前後左右に重心を移動させてストラテジーが出るかどうかをみます。
この練習を繰り返すだけでもバランス訓練、筋力訓練になります。実際にどういう反応がでてるのか、どのくらいまでバランスが取れてて、どこから崩れるのか、しっかりフィードバックしてあげることが重要です。
そしてステップ反応の練習もしていきます。この時に重要なのが「足を出す」練習ではなく、「重心が逸脱した結果、足が出る」練習をすることです。先に重心を逸脱させることをしなければなりません。ただしこの練習については恐怖心が強い方が多いです。そのためまずは治療者が支えた状態で行ったり、いつでも掴まれるものがある状況で練習を実施することが重要です。
このようにバランス練習といっても単に筋力が弱いから筋力を強化しようではなく、バランスの取り方を評価してどういう練習が必要なのか判断しなければいけません。ピタっと止まることだけがバランスではありません。重心の動揺や逸脱に対してどう修正するのか、そういった能力を鍛えていくことが必要です。
デイサービスセンターあ・ふる~るにはリハビリの専門職である、理学療法士・作業療法士が在籍しております。バランスに不安をお持ちの方は是非あ・ふる~るにご相談ください!!